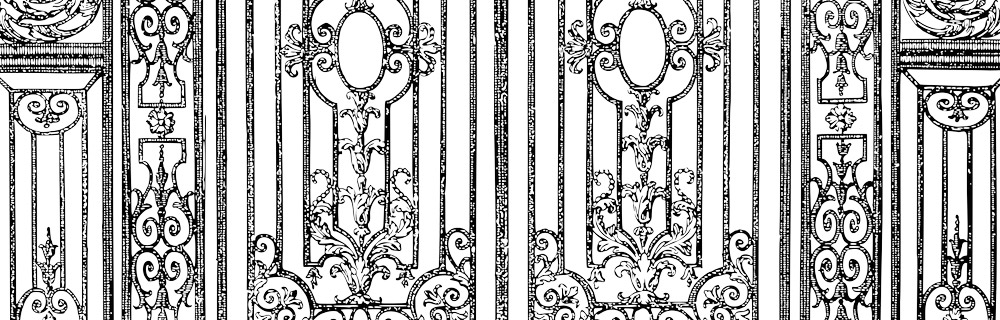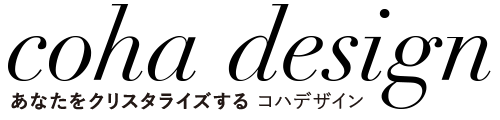自分用のメモノートです
誰も読まへんやろ〜こんな記事、と油断して書いていたら、友人たちから「この記事イイネ!」と反応をいただき、「えっ読まれている🤯」と驚き。

まだまだまだまだ内容を追加していったり、修正していくイメージです💡
わたしはド素人の、知的探求心のみで、なかではソースがはっきりしていそうだな? と思う文献を辿ってみようと努力している個人に過ぎないので、皆さんの意見ではなく、情報補佐やご自分の見解を固める前の1材料として楽しんでいただけると嬉しいです。
ちなみに…この「油断」について、先日みかけた素敵な内容があったので添えます。
「伝統」という日本語は本来、「伝燈」という字が元で、これは「お釈迦様亡きあとに何をよりどころにして生きていったらよいのか?」と嘆いた弟子たちに対して、お釈迦様が
「私をよりどころにするのではなく、真理とあなた方が真理を追究したいと思う志をともしびとしなさい」と教えを遺したという語に由来しています。
「油断」の語源も、この(筆者注:この燈火が燃え続けるために必要な燃料である)油を絶やすことからきているとされています。
――『コンセプト・センス』吉田 将英 (著) この本めっちゃ良かった〜!! オススメですっ📖☺️

健康のために、真理のためにも、油を断ってはならぬのじゃ〜っ🔥 って感じがして、なんだか好きな言葉になりました☺️♥️
アンチ・ニュートリエント(反栄養素/抗栄養素)について
①🥜🍆🥒レクチン
豆類や全粒穀物などに含まれるタンパク質で、過剰に摂取すると腸壁に影響を及ぼす可能性がある。加熱または発酵することで失活させる必要がある。
- インゲン豆(国内で2006年に健康被害事例あり)、ピーナッツ、大豆などマメ科【フィトヘマグルチニン(レクチン)】、アサ科、シソ科(チアシード)、ゴマ科
- 全粒穀物(キヌア、大麦、玄米など)
- ナス科(ピーマン、ジャガイモ、トマト、スイカなど)
- 特に高いレクチン活性はインゲン豆、大豆、エンドウ豆、ヒヨコ豆、レンズ豆(らしい)
フィトヘマグルチニン毒素を分解するには、豆を水に浸して完全に茹でる必要がある(たとえば、少なくとも12時間浸した後、最低10分間沸騰した湯で調理する)。
研究によると、たとえ豆を85度で1時間加熱調理したとしても、フィトヘマグルチニン毒素は依然として活性を維持していることが示されており、毒素を除去するためには、豆を低温調理(土鍋やスロークッカーを使用するなど)してはならない。
豆類は水に浸した後に、十分に茹でる(100℃)必要がある。

豆腐、豆乳はどのくらい浸水させて加熱調理しているかが分かれ目なのかな? あるいは失活の%はあっても、成分としては残っているのかも🤔 後述する東北大学の研究では、他の成分との兼ね合いによるのか高温でも残留が認められた様子でした
💡大豆食品のなかでも発酵させていない、しかも沸騰状態で加熱していない調理法による豆乳や豆腐を毎日大量に食べていたら、あるいはかなり毒性を得てしまうのかもしれないなぁ
②🥔グリコアルカロイド(ソラニン、チャコニン)/🍅トマチン【レクチンの一種】
グルコースやガラクトースなどの「糖」と、窒素を含んだアルカリ性物質「アルカロイド」からできている「グリコアルカロイド」の一種(農水省)
ジャガイモは【ソラニン】(芽を避ける理由)、青いトマトは【トマチン】など(トマトの皮むきをする理由、植物毒は種と皮に多く含まれるから)
じゃがいもに光が当たったり、傷がついたりすると、グリコアルカロイドの量が増えます
国内で市販されているじゃがいも5品種(品種ごとに各5点:いずれも芽がみられないもの)中のα-ソラニンやα-チャコニンの濃度を調べたところ、5品種全てにおいて、皮層部(約1 mmの厚さでむいた皮)に高い濃度で含まれ、髄質部(ずいしつぶ:皮層部を除いた部分)にはほとんど含まれていないことが報告されています。
「先生、暑いですけど元気ですか?」
「いや、いま気持ちが悪くてフラフラするんだ」
「え? 何があったのですか?」
「いま青いミニトマトを我慢して5個食べたら、フラフラするんだよ」
「先生知らなかったんですか? 未熟なトマトには毒があるんですよ。緑色の未熟なトマトは食べられるのかと言う質問は、夏休みの間に博物館に来る質問数の上位に来るんですよ」。
💡緑色のまま、あるいは緑色になったり芽が出ているものはNG、種や皮まわりは意識して捨てることが助けてくれそう。そこまで強く意識しなくていいような気もするけど、腸壁が弱っているときは、わざわざリスク高いものを取りに行かないほうがいいきもする。あとは、保存状態や劣化具合? にもよりそう。
③🌾🌻🥜フィチン酸(フィチン塩酸)
フィチン酸は、カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛とキレート化する=ミネラルの吸収を阻害する可能性がある。
- 種子類(ゴマ、亜麻仁、ヒマワリの種など)
- ナッツ類
- 豆類、全粒穀物(玄米など)
💡種子や豆類を発芽させることで、フィチン酸の含有量を減少させることができる。ということで、玄米を食べるなら気持ち精米するか、水にめっちゃ浸けておくか、よく噛む(これは気持ちだけの作用かもしれないが)などで消化しやすくすることを頑張るとかなのかなぁ。
④🥬🥜シュウ酸(シュウ酸塩)
シュウ酸はカルシウムの吸収を阻害します。腎臓結石の原因にもなります。野菜を茹でることで水溶性のシュウ酸を減少させることが有効。
- ホウレン草
- アーモンド、カシューナッツ、ピーナッツなど
💡カルシウムに関してはカルマグバランス他、いろんな要素が絡んでいる気がするけれど、生のホウレン草は控えておいた方が無難?
⑤🍞🍕🥐グルテン
グルテンは、小麦や大麦、ライ麦などに含まれるタンパク質で、一部の人々に消化器系の問題を引き起こすことがあります。特に、セリアック病の患者やグルテン感受性のある人々では、グルテン摂取が腸の炎症や栄養吸収不良を引き起こす可能性。
- 小麦、ライ麦、大麦、麦芽トリティケール(ライ麦と小麦の交配種)
薬用石鹸(に含まれた成分:加水分解コムギ末)により小麦アレルギーが引き起こされ問題となった事件は大きな騒動となりましたよね🤔
ちょっと興味深いと思ったのが、日本と国外による「グルテンフリー」表示の基準が違うというもの。

日本は数ppm以上でアレルギー表示を要するが、EU・アメリカにおけるグルテンフリー表示はグルテン濃度が20ppm以下とのこと、日本の方が基準が厳しいってことなのかな。このPDFによれば、国外のグルテンフリー表示はセリアック病の人への選択基準として設けられているらしい。
代表的な食材別で眺める反栄養素
🌾玄米
レクチン
フィチン酸
アブシジン酸
ヒ素(というけど、農水省のデータ2019年を見ると、玄米 / 精米のヒ素の値(mg/Kg)は、最小値が 0.03 / 0.02、最大値が 0.60 / 0.25、平均値は 0.17 / 0.098 とあり、これは大差があるのか自分には分からない)
カビ毒
日本でも、2011(平成23)年に、国内で生産された米が毒性の強いかび毒であるアフラトキシン類(アフラトキシンB1)によって汚染された事例が確認されています。
農林水産省が実施した中小規模の穀類乾燥調製施設の真菌類(かび)の実態調査では、乾燥調製施設の塵や埃の中に、アフラトキシン類などの毒性の強いかび毒を作るかびを含むかびが広く存在していること、塵や埃の量が多いほどかびの量も多いことを確認しており、米や施設の管理を誤れば、米にかびが生えたり、かび毒汚染が起きたりする可能性があることが判明しています
米・米粉をめぐる状況について(令和5年2月15日)農水省 九州農政局

ってことは、ものすご〜いこだわった玄米でホコリまみれの保管所にあるものより、慣行栽培でクリーンな部屋に管理されていた玄米の方がわたしは安心だなーと感じた次第です…カビ毒の方がすぐ体に出るダメージ強そう…
🍞小麦
グルテン
主な栄養素はタンパク質、ビタミンB、無機質(特に鉄、リン、亜鉛、カリウム、マグネシウム)無機質はフスマに多いため、損失も多い。
抗栄養素にトリプシンインヒビター、アミラーゼインヒビターが含まれる。
フィチン酸が無機質をキレート化し、ミネラルの利用を低下させる。

みんな腸活=グルテンフリー!! っていうけど、グルテンは消化しづらい以外で具体的にどんなデメリットがあるのか、そんなに腸に害があるのか、文献が見つけられないんですよね…カビ毒とか未消化物が溜まってるうえのグルテンは問題だろうけど、最初にやるべきことってグルテンフリーじゃない気がするんだけどなー(まぁ現代においてグルテンを避ければ、他のものも自然と避けやすくなる分かりやすさはある)
🌱大豆
トリプシンインヒビター、レクチンなどの抗栄養素が含まれ、未加工の大豆は食品に適さない。
大豆の主な成分はトリグリセリド(中性脂肪)で、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸の含有量が比較的高い。ビタミンKとEの供給源と考えられている。
エストロゲン作用、抗エストロゲン作用、低コレステロール作用をもつイソフラボン、リン脂質、ステロール類、サポニンが含まれる。
- 農薬の使用量が非常に多い(らしい)
- ほとんどは遺伝子組み換え(らしい)
- 日本で流通しているものはアメリカ・カナダ産が多く、ほとんどはラウンドアップなどの農薬が使用されている(らしい)
遺伝子組換え食品についての国の発表
大豆、豆乳、豆腐にまつわる大冒険
健康オタク界隈で言われている、大豆の害
別の問題は植物性のエストロゲンです。たくさんの人は更年期障害の症状改善に効果があると信じていますが、実際には症状を緩和する事はありませんし、特に幼児や小児には悪影響を及ぼしかねません。どの製品が大豆を使っているかを確認してください。それらを避けることを強くおすすめします。
まず、最も重要な事は市場に出回るべきではないという事です。流通は禁止され市場から取り除かれるべきです。ここで再び大豆の人工乳の類について強調したいことは、2万倍の量のエストロゲンが確実に子供たちの血流に入り込むのですが、産業界は「そんなことはない」と言っていることです。
豆乳は危険な毒物であるマンガンとアルミニウムを高レベルで含んでいます。このようなものが市場に流通していることについて、私は理解に苦しみます。しかもそれは、一般的に乳児に与えられる商業的な人工乳での話です。あなたの場合、いかなる市販の人工乳も使うべきではないでしょう。
豆乳もまた、代謝が低下する問題となる食べ物のひとつです。分離精製した大豆たんぱくや植物たんぱくも避けるべき食品です。それは、あなたのキッチンで作られたものとは違うのです。
それは大きな商業的工場で製造されたもので、通常は漂白され、アルミニウムの容器に入れられ、アルミニウムを含みます。そして、それらには大量のグルタミン酸ナトリウムが添加されています。

これ端的にまとまっているなーと思って記載しましたが、彼が言っていることのデータがないので、わたしは話3分の1で受けとってます。これを観ている方、これをそのまま真に受けてインストールしないでね。
このMercola博士は、例えば自分の健康食品にまつわるオンラインショップがあります。ある意味、ポジショントークでもあるのです。
Amazonベストセラーとして、COVID-19の真実っちゅー本も出しておられるそうな。うーん、いかにもだぜ…レビュー7,000件超えよ! 熱狂的だわ。感情的なフォロワーが多いのかもしれぬ。
💡まだこの人の職歴とかヒストリーを辿りきれていないので、検証中です。
豆乳だけではなく、豆腐などの水気を多く含む大豆にも、より多くの反栄養素が残っているので気をつけましょう。
では、反栄養素を含まない大豆製品はあるのか。実は、反栄養素を取り除く方法が一つだけあります。それが、発酵です。
なので、味噌と納豆は一番いい大豆食品と言えます。
ただし、反栄養素を腐食させるには、時間をかけて発酵させることが大切。味噌や納豆を購入する際は、昔ながらの正しい製法で作られたものかをしっかりと確かめるようにしましょう。
日本で豆乳が飲まれるようになったのは、1960年代の初め。
世界最大の大豆生産国アメリカからの情報によって豆乳が推奨されるようになってからです。(アメリカは世界の大豆生産の50%以上を占め、アメリカ産の大豆90%以上が遺伝子組み換えです。)

こちらのオーガストさんも、端的にまとまっていて、そして豆乳=イイモノ!って健康オタクは思いがちなので、あえての投石としてここで載せていますが、彼の内容も論文がベースになっているとはいえ臨床試験とかされている人ではないので、3分の1くらいで受けとっています。何より彼は治療とかアトピー・アレルギーケアじゃなくて、老化したくないチームなので目線が違うところも注意だと思います。
具体的にいうと抗酸化=酵素がいいとか、RAWがいい! っていう強烈なフィルターと(太りたくない、若く美しくありたいという強い原動力からの情報サーチであること)
抗炎症=不健康かもしれないね?という目線がない気がします。だから慢性アレルギーや症状がある人は真似すると危険なことがあるかもしれないです。
彼もオンラインショップで各種サプリなど販売しているから、ポジショントークでもあるのです。
で、
彼のいう、豆乳は昔の🇯🇵で飲んでなかったのに🇺🇸に商業的に持ち込まれたんだ! っていう言説、歴史ではどういう事実があるのかな? という旗が立ちました。
東城百合子さんから見つめる、豆乳=大豆ミルクの信仰心?
元々、自然療法ルーツを調べているとき、東城百合子さんの生涯や、そこで外せない重要な出来事、キーパーソンをワ〜ッと眺めていたときに

(ご存知でしたか? 東城百合子さんはかなり神への信仰心が強くキリスト教徒でもあって、かつ四柱推命も大好きだと自著に書かれているのです。ある日本人宗教家にも強く憧れを感じておられ、人生の師だと仰いでおられますが、そうした人生の師だと述べているアメリカ人が大豆ミルク=豆乳を日本に信教しにきたキリスト教徒=セブンスデー・アドベンチスト教会のお偉いさんなんですわ)
その頃、米国から、国際保健機構の理事で、国際栄養研究所の所長を務めていたハリー・ホワイト・ミラー博士が来日する。ミラー博士は大豆ミルクの権威であり、製造法の指導に来たのだ。わずか2週間の滞在だったが、ミラー博士の人格と哲学に触れた東城は、人生の師として生涯ミラー博士を仰ぎつづける。
結婚後子どもも生まれ、充実した日々を送るが、夫の五来長利に、沖縄の食品会社から、「大豆ミルクをつくりたいので協力して欲しい」と連絡がはいったのは、そうした時期だった。
でも、わたしたち日本人で、自然療法が好き♥️ とか、豆腐や豆乳がヘルシー! って言ってる消費者も、なんなら豆乳販売会社だって博士のこと出してこないですよね。名前も聴いたことがない日本人の方が多いと思う。
Wikipedia でも、日本語にはなく、英語圏ならありました。
大豆ミルクの立役者、ミラー博士とはどんな人物なのか?
「中国の医師」として知られるミラー博士(伝記ではその称号で呼ばれています)は、世界的に有名な宣教師の医師および外科医であり、世界中に 15 を超えるセブンスデー・アドベンチスト病院を設立しました。
彼は西洋に大豆と大豆食品の大きな可能性を目覚めさせることが自分の責任であると考えていました。
ミラー博士は、アジアにおける現代の豆乳復興の創始者ともいえます。
中国での初期 (1903-11)。1903 年 10 月、ミラー博士とモードは、別の医師夫婦とともに中国に向けて出航し、日本に短期間滞在しました。
ミラー博士は後に(1962年)、中国人や他の東アジア人の多くが、豆乳は腸の不調を引き起こすと信じているためあまり飲まないが、豆腐はそうではないと語ったと述べています。おそらくこれが、豆乳が一般に乳児や子供に与えられなかった理由でしょう。
中国における豆乳の先駆者(1925-39)
病院には孤児となった乳児がどんどん増え始めた。乳児が食べ物を見つける唯一の望みは乳母を見つけるか、牛乳を飲ませてもらうことだったが、中国では牛乳は非常に高価で、乳児全員が牛乳を飲めるわけではなかった。ミラーは、風味と消化性が良く、母乳と同等の栄養価に調合でき、低コストで、保存期間の長い豆乳を開発しようと決意した。
1930 年代半ばのある日、彼が施設のキッチンで豆腐製造機のスラリーを扱っていたとき、突破口が開かれた。彼は後にこう書いている。「背後から神の声が聞こえた。『生蒸気でもっと長く煮たらどうだ』」。彼は、それ以前に誰かがそんなことをしたことがあるとは知らなかった (Blix 1980)。やがてスタッフと患者は、味と消化性が向上したことに気づき、彼は均質化の際に大豆油かピーナッツ油を加えて、さらにおいしくした。
1937 年 5 月 4 日、上海の豆乳工場がまだ全盛期だった頃、ミラー博士は豆乳製造法で米国特許番号 2,078,962 を取得しました。博士は豆の風味をなくす方法と、遠心分離機とホモジナイザーの使用法を紹介しました。特許では、博士は自分の製品を「植物性ミルク」と呼んでいます。
新生児が死なないための、高価なミルク以外の選択肢として、おそらく非常に難易度の高いテーマにチャレンジなさった末の試行錯誤で生まれた新しい答えだったんですね。
この情報によれば、導入設備を略奪していった日本軍
で、驚いたのが日本軍。
第二次世界大戦が始まる前に、ミラー博士は国際栄養研究所の支部と豆乳工場をフィリピンのマニラのナグタハン41番地に設立していました。
ミラーは、日本軍の攻撃を受けたとき、フィリピンで工場の設立を手伝っていました。戦争中、日本軍は豆乳製造設備をすべて盗みましたが、建物には被害を与えませんでした。
ここでは紹介しませんが、大豆ミルクや豆乳を国会図書館デジタルで🔍️すると、戦前くらいかな? 1950年ごろの書籍で、日本人学生への教科書として「大豆ミルクの作り方」が出てくるんです。あとはお母さん向けの食養生を解く教科書っぽいものでも。どのくらい一般認知度が高かったのか、マニアックだったのかは分かりかねますが。
そのくらい、国策として安価で良質なタンパク質の確保は逼迫した課題であり、そこに対する素晴らしい答えとしてもてはやされ、教育されていたのかもしれません。
そして、ミラー博士😢ってなるエピソードも…
マウントバーノンにある大豆乳製品工場で、ミラー氏はいつも一日の仕事を真っ先に始める人物だった。ある日、新しい配合を試していたとき、フードグラインダーで指の先を切断してしまった。彼は静かに切断部分を拾い上げ、オフィスに入り、縫い付けた。
いやあ、こんな方がはるばる日本の沖縄に来て、みんなに大豆ミルクの作り方を教えるよ、ひいては子どもたちが死なないためにって言ってたら、たかだか2週間だけの時間でも、東城百合子さんが人生の師って崇めるのじゃないでしょうか。
辰巳芳子さんと大豆100粒運動
やはり健康オタクにおける崇拝者? 絶対のオピニオン・リーダーとして有名で人気な辰巳芳子さんも、大豆100粒運動を始められ、本も出されています。
「世界的な食糧難が予測され、国と国との対立が激しさを増すであろう21世紀、人類は豆に頼らねばならぬ時代来るのではないか。そのとき、日本人が頼るとしたら、「大豆」をおいて他にないのではないか」とも述べています。昔から日本人はタンパク源を大豆からいろいろな形で摂取してきています。高い栄養価に加えて、日本の食文化における大豆への価値観がそこに浮かんできます。
我が国の大豆の自給率は現在4%内外に止まっており、如に世界貿易上の課題、内外価格差の問題があるとはいえ、その生産は消滅寸前の状態と言わざるを得ないところに立っています。

たぶん、辰巳芳子さんのレシピでは豆もちゃんと浸水・湯でて毒素を排出したものであり、豆腐や豆乳をひたすら食べれば健康になるといった言い方はしておられないと思います。あくまで今後また戦時中のように食糧が足りなくなって(自給率低すぎ)いく際の、子どもたちが摂取できるタンパク質として育てやすい大豆をフィーチャーしているのだと感じています。
が、彼女たちが説く大豆の素晴らしさだけを受け取り、安易に「こういう下ごしらえだと楽ちん♪」「豆乳・豆腐でお手軽スイーツ♥️」みたいなレシピがブワ〜っと拡散され、かつ「これで腸活」というレッテルが貼られているんじゃないかなあ…
それは危ないよと思う…皆さんはどう思いますか?
▼その後のミラー博士の続き
アメリカに大豆食品を紹介していた間、ミラー博士はアメリカ大豆協会の最も積極的な支持者の一人で、大会で定期的に講演し、Soybean Digestに記事を寄稿していました。彼の最初の講演は「人間の栄養における大豆の役割」(1940 年)で、最初の論文「大豆と東洋」(1943 年)に続き、「大豆で世界を養う」(1946 年)、「東アジアの大豆食品の調査」(1948 年)など、参考文献に記載されている論文が続きました。1958 年 9 月、彼は協会の名誉会員となり、金メダルを授与されました。
1930 年代後半には、ミラー博士が東アジアにまいた種が芽を出し始めました。20 世紀後半にアジア全域で起こった豆乳への関心と豆乳生産の目覚ましい拡大のほとんどは、ミラー博士の研究に端を発しているというのは興味深いことです。
1953 年、74 歳のとき、彼は 3 度目の結婚をしました (妻は 35 歳くらいでした)
学校で豆乳工場を開設し、学校、サナトリウム、および周辺地域に毎日豆乳を供給しました。1956 年、ミラーが台湾を離れる時が来たとき、蒋介石総統は、豆乳の使用で何千人もの乳児の命を救い、約 12 のサナトリウム病院を設立するという中国国民へのたゆまぬ奉仕に感謝して、中国最高の勲章であるブルー スター オブ チャイナをミラーに自ら授与しました。当時、ミラー氏の元患者だった大元帥は、療養所の豆乳が大好きになり、補給のために上海まで1,000マイル以上も離れた自家用飛行機を飛ばしたこともあったと回想している。
ハリー・ミラーは、中国人が「偉人」と呼ぶものの輝かしい例です。彼は、人間と非人間を問わず、すべての生き物の福祉に人生を捧げました。彼は、与えることに真の喜びを見出し、自発的に質素な生活を選びました。親しい仲間の推定によると、専門職の報酬だけで、彼が関わっていた病院、教会、栄養学の仕事に約 250 万ドルを寄付しました。彼の人生の中心にあったのは精神的な価値観でした。
(筆者注:ブラウザによる日本語への自動翻訳です)
三育学院 (日本ユニオンカレッジ) と連携して、アドベンチストが運営する三育食品の豆乳工場の設立にも協力しました。この工場は日本初の大手豆乳製造会社となり、現在では日本最大の豆乳工場の 1 つとなっています。
すごいお人だがや。キリスト教の素晴らしさって、ひとえにこういう奉仕活動ですよね。キリスト教の負の側面も間違いなくあると、自分は思うのですが。わたしもその負の側面でくるしい子ども時代を過ごした人間として。
▲本当だとしたら、キリスト教の捉え方が180度ヒックリ変える大切な視点が書かれています
んだば、大豆にあるレクチンとは、どうすれば取り除けるのか?
大豆に約0.1%含まれるレクチンは、N-アセチルガラクトサミンに対して結合特異性を示すだけでなく,リンパ球の幼若化を惹起するなどの多様な生理活性をもっている.レクチンはトリプシンインヒビターと同様に食品加工や調理において加熱失活すると理解されているが,各種大豆加工食品の多くには残存するレクチン活性がみられ,特にきなこや炒り豆のように乾燥状態で加熱加工したものには強いレクチン活性が検出される.
本研究では,大豆食品に含まれるレクチンを生体機能調節因子として積極的に活用できるか否かを検討することを目的として,レクチンの加熱,pHおよび各種消化酵素に対する安定性を調べるとともに,マウスに経口投与した大豆レクチンの消化器官における挙動と腸管からの吸収性を調べた.
レクチン活性の熱安定性
*本記事筆者による注:以降、SBA=精製大豆レクチンの略
食品加工および生体内でのSBAの安定性に対するpH,温度,消化酵素の影響を調べた.SBAをpH3m(50mM酢酸ナトリウム緩衝液),pH5(同),pH7(50mMリン酸ナトリウム緩衝液),pH9(同)に溶解後,50℃,70℃,90℃で加熱処理した.
90℃ではいずれのpHでもレクチン活性は急速に減少し,30分以内に活性は未処理の6%以下になった.
70℃では,pH3のSBAは1時間で失活したが、その他では3時間の加熱でも未処理の12%の活性を保持していた.
50℃では,pH3と7で活性が短時間に1/2に低下したが、それ以上の活性の低下は3時間後にもみられなかった.
以上の結果より,SBAを高温で処理すれば短時間でレクチンを失活させることが可能であるが,通常の生理活性たん白質に比べれば高い安定性を持っているといえる.
大豆に一晩給水させて作った豆乳を80℃に加熱したときのレクチン活性の低下は,SBAのみの場合に比べて50%遅くなった.これは,SBAの熱安定性がグロブリン(筆者注:タンパク質の一種)や他の成分によって向上したためと考えられる.
要約
大豆レクチンは,90℃に加熱すると急速に活性を失ったが,80℃では2時間の加熱でも活性を維持した.また,豆乳のように他の成分が共存する複合系においてはレクチン活性の安定性が向上した.弱アルカリよりも弱酸性から中性で高い安定性がみられた.
マウスに経口投与したレクチンの挙動を酸素免疫測定法および蛍光標識法で追跡し,小腸管壁における未消化レクチンの存在とその一部の断片化,および分子量約4,000のレクチン断片の血液への取り込みを確認した.血中のレクチン断片は,投与1時間後から増加し,4ないし6時間後に最高レベルに達した.

市販の、あるいは手作りする豆乳・豆腐では、どれくらいその毒素は取り除けているのか? 紀文とかお豆腐屋さんに何度で何時間加熱するか、レクチンがどれくらい失活しているかのデータ表示があったらいいんだけど…大手だったら問い合わせれば教えてくれるかもしれませんね。
だけど、豆乳とかは特に、風味を壊さないみたいな言い方で、いっても80度くらいのところも多いのじゃなかろうか。どうなんだろう。あとは風味を調える(豆臭さを緩和したい)ために大豆油、なんらかの植物油を添加、しかも揮発させたり高温で入れているんじゃなかろうか。どうなんだろう?
豆類であれ、野菜であれ、果物であれ、多くの植物性食品にはレクチンが含まれている。これらの物質は植物を病気や害虫から守る働きがある。しかし、ヒトにとっては有害である可能性もある。それには、レクチンの量と種類が決め手となる。適度に摂取すれば、ほとんどのレクチンは無害である。
しかし、生の豆類に含まれるレクチンのファシン(Lektin Phasin)には健康上のリスクがある。赤血球を凝集させ、胃腸障害を引き起こす可能性がある。大量に摂取すると、極端な場合、命にかかわることさえある。
BfR副所長であるTanja Schwerdtle教授は、「良いニュースは、レクチンは熱によって破壊される可能性があることである。したがって、豆類は常に推奨される調理法に従う必要がある」と述べている。
生の豆類は沸騰したお湯で30分以上煮る。乾燥豆類は少なくとも5時間浸漬させた後、浸漬水を捨て、新鮮な水で調理する。穏やかに蒸す等の優しい調理法はほとんどの豆類には適さない。
スナップエンドウやえんどう豆はレクチンの含有量がごくわずかであるため例外である。適度に生で摂食可能である。これは、トマト、マッシュルーム、バナナ等、レクチンを含有する他の多くの食品にも当てはまる。
レクチンの望ましくない影響は、主に豆類の間違った調理法のために起こる。
例えば、現代の調理法において、野菜は穏やかに加熱調理されることが多いが、これにより野菜の食感が残り、ビタミンが失われにくい。しかし、豆類、ひよこ豆、レンズ豆等を調理する際には、十分な加熱と調理時間が重要である。
例えば、インゲン豆の種やさやにはレクチンのファシンが含まれている。生の種子を少し食べただけで、腹痛や吐き気が起こることが多い。ひどい場合は、血の混じった下痢、発熱、血圧低下が起こることもある。症状が出るかどうか、どの程度重症かは個人差が大きい。特に子供は体重が少ないためリスクが大きい。
少なくとも腸壁が荒れている、なんらかの炎症が起きている人は避けるべきでしょう。と、わたしなら考える。害だけではないとしても、ダメージが強く出てしまうときならば。
レクチンは、生物内で免疫機能など重要な役割を担っていると考えられていますが、中には食品として摂取すると腸の粘膜細胞と結合して炎症を引き起こし、腹痛、下痢などの健康被害の原因となるものがあります。
生の豆に含まれるレクチンはこれに該当し、通常のゆで方で加熱すれば変性・分解して不活化するため何ら問題はないのですが、不十分な加熱状態で摂取すると、健康に悪影響を及ぼすことがあります。
また、米国食品医薬品局(FDA)の文献でも、スロークッカー(電気低温調理器)、電気鍋、土鍋(キャセロール)などでいんげんまめを調理した際、加熱が不十分なため健康障害が発生した事例が報告されています。
https://www.mame.or.jp/Portals/0/resources/pdf_z/071/MJ071-06-MS.pdf